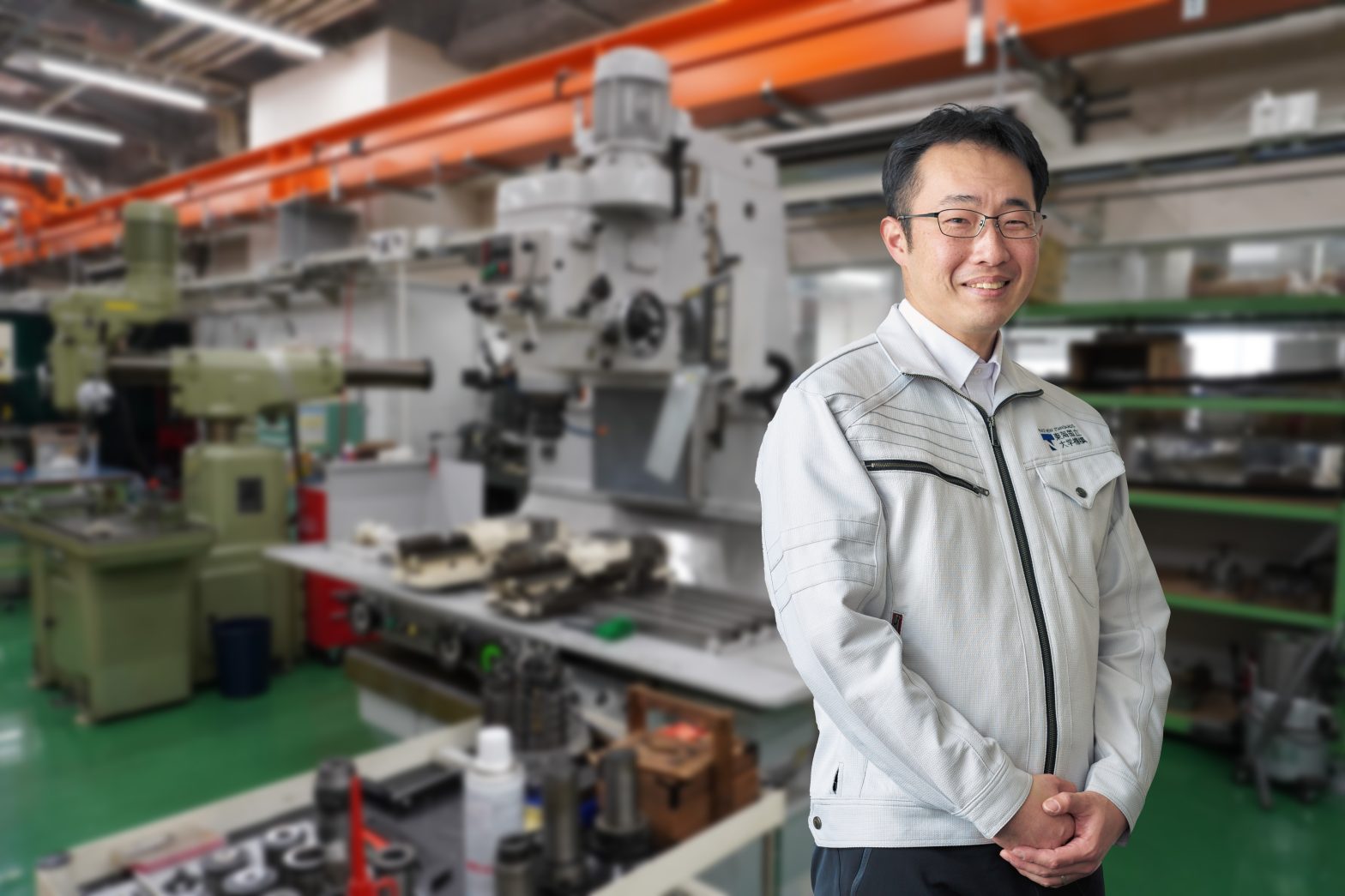技術職員インタビュー
06
"寄り添う"技術を模索する
Goto Shintaro
名古屋大学
技師, CFA
後藤 伸太郎
[ 専門 ] 機械加工、電子工学、機械工学、材料力学、実習支援、教育支援、実験研究支援
■ 経歴
愛知県出身。幼少期から工作が好きで、割りばしや段ボール、乾電池などでピタゴラ的装置を作っていた。名古屋工業大学第二部に通い、学生フォーミュラの活動にのめりこむ。卒業前から技術職員として同大学に勤務し、のちに、名古屋大学へ転出・転入した。業務として主に研究室からの実験装置の設計・製作依頼を請け負っており、近年では所属する工学部だけでなく他学部からの依頼にも対応している。以前、請け負った製作業務において、担当教員が特許の出願を思案していたことから興味を持ち、知的財産管理技能検定2級にも挑戦、2025年合格。
昼間働いて夜は学生という二足のわらじ
——— 学生時代、何かに熱心に取り組んだ経験はありますか?
あります。私は名古屋工業大学の第二部(夜間部)に在籍する中、1年生から3年生まで部活動で、学生フォーミュラの活動に熱中していました。第二部は5年制で入学当初はたくさんアルバイトを経験しようと考えていましたが、結局生活が部活動中心になって思っていたよりも働けませんでした。そのため、疎かになりがちだった学業と4年生からの就職活動のため3年生の大会までで部活動には区切りをつけました。
——— 学生時代から技術職員として業務に従事していらしたとのことですが、どのような経緯で技術職員になられたのでしょうか?
部活動に区切りをつけて、いざ「就職活動だ」と考えながら学内を歩いているときに技術職員の方から「大学で働かないか?」とお誘いを受けました。部活動において必要な工作をする際に技術職員にお世話になる事が多く、部活動に勤しんでいた私のことをよく知ってくださっていたようです。はじめはアルバイトのお話かと思ったのですが、正職員としてとのことでした。
無事に就職でき、5年生からは昼間は技術職員として働き、夕方以降もそのまま職場である大学で、今度は学生として授業を受けるという、文字通り朝から夜まで大学にいる日々でした。入学時は正直、「大学は、将来職に就くための “人生の通過点”」くらいに考えていたというのに、人生はわからないものです。
技術職員として目指す姿
——— 名古屋大学では、どのように業務をこなしていますか?
主に学内の研究室の教員や学生からの依頼で研究に必要な装置の設計・製作を行います。私の所属する装置開発技術支援室では、技術職員が各々技術支援を行えるようにするという指針があります。
学内には、多種多様な工作機械がありますが、装置開発技術支援室に所属する技術職員は、どの工作機械も操作でき、依頼者の打合せから設計・製作、納品までを行えるということです。プレッシャーもありますが、知識と技術が幅広く身につく業務です。依頼者の多くは、まず相談という形で来られます。設計図やポンチ絵のような、一目見て用途やしくみがわかるものを用意してあることは稀で、多くの場合、「こういう実験がしたい」「このような感じの○○を作ってほしい」というぼんやりとした内容です。相談の中で必要とされる機能を聞き取り、装置の構造や材料を考え、CADを使って依頼者と完成イメージを共有します。齟齬のある状態で業務を進めないようしっかり打合せをすることが大切です。依頼者が当初想い描いていた装置より便利で安全な装置が出来上がり、喜んでもらえると私もやりがいを感じます。
それから、実習授業やものづくり公開講座にも携わっています。ものづくりに興味のある学生が楽しそうに部品に触れているのを見ると、嬉しくてつい助言したり手を差し伸べたりしたくなってしまいます。




——— 最近、農学部の方からも試験機の不具合で相談があったと聞きました。
はい、ありました。もともと実験器具や備品など、「ちょっと調子が悪いから、見に来てほしい」と呼ばれることはよくあります。一部の部品が破損していたり、設定が狂っていたりと原因は様々です。このときは農学部で使用してきた複数の油圧疲労試験機に関しての相談でした。見させていただいた結果、油圧ホースの劣化、摺動部の摩耗、作動油冷却器の破損があることが分かりましたが、私は油圧装置のことは詳しくなかったため経験の多い先輩職員にアドバイスをもらい対応しました。
——— 技術職員として、研究や実験に関連した業務に携わるときにどんなことを大切にしていますか?
「研究者に寄り添った技術提供をすること」を常に念頭に置いています。私たちの職場は、毎日異なる業務を行います。製作する部品や装置のほとんどが一品もので、いわゆる「少量多品種」です。そのたびに、「今度の依頼品はどうつくろうか、精度を出すならこうだろうか、機械はあちらの方が良いだろうか」と考えながら対応していくことになり、この積み重ねの中で自分の知識や技術もアップデートされていきます。過去、職場見学に来られた方の中には、「大学職員なのだからルーティン業務だろう」とおっしゃる方もいましたが、そんなことはありません。ここは、日々自ら知識と技術を追い求める職場です。それはつまり、「自分で考えてものづくりすることが好き」という人にはとても合った職場であるとも言えます。
そして、研究というのは専門性が高いので、自分の今までの経験からさらに踏み込んだものが必要な時もあります。私は日ごろから学びを怠らないことが「研究者に寄り添った技術提供」につながると信じていますし、それがさらに「研究者にとって嬉しい技術支援」になれば私も嬉しいです。
——— そういった志を持つきっかけとなった出来事はありますか?
実は過去、依頼者の方が私の担当した実験装置について「特許出願を考えている」というお話をされたことがありました。この装置は、町工場や民間企業の内製部門で受注を断られたもので最終的に全学技術センターに依頼が来て、私が担当し完成させることができた装置でした。当時は「簡単な工程を組み合わせただけなので特許にはなり得ないと思う」と話してしまいました。しかし、その組み合わせのアイデア(製作方法)が特許となりえたかもしれないと後になって知りました。あのとき知識があれば、喜んで特許出願にも協力したかったのに…そんなこともあり、「より研究者に寄り添うためになにができるか」と考えた末、知的財産管理技能検定への挑戦を決意し、2級に合格することができました。現在も特許について相談に来られる依頼者はいますので、これで最低限の「寄り添い」はできます!
個性あふれる同僚たちと刺激し合う日々
——— 加工の技術も知財の知識もあって、技術支援室ではかなり頼りにされる存在でしょうね。

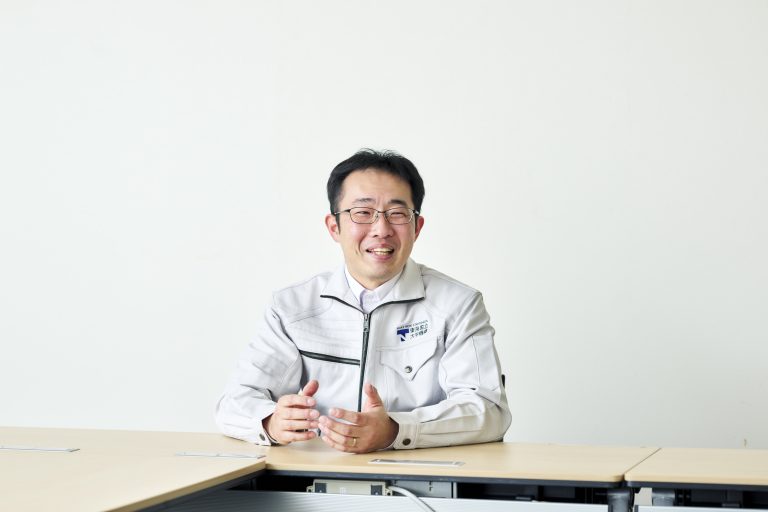

どうでしょう。実は、知財管理の試験挑戦は、自信のなさを払拭したい気持ちもあって決めたんです。令和3年度、コアファシリティ構築支援プログラムに採択された東海国立大学機構では、技術職員組織の中でCFA(コアファシリティアドミニストレーター)という役割が新たに設けられました。コアファシリティとは大学の研究基盤設備・機器の共用化推進の取り組みですが、主体となるものは機器分析用の装置であることが多いため、CFAには分析系の技術職員が大半です。どの方もそれぞれの専門知識を活かし、担当分析機器の高度な運用に力を注いでいます。私は、お誘いいただく形でこの役割に就いたのですが、「分析系の技術職員ではない私はどのように貢献できるだろうか」と考えることもあります。そんな状況もあり、守備範囲を広げたいという気持ちが自然と大きくなりました。同時にこれまで経験を積んできた装置開発においてもより深めるため、電子制御分野の技術習得にも励んでいます。電気も機械も両方できることは装置開発においての「鬼に金棒」となると信じています。
[本記事内容は2025年度に取材したものです]